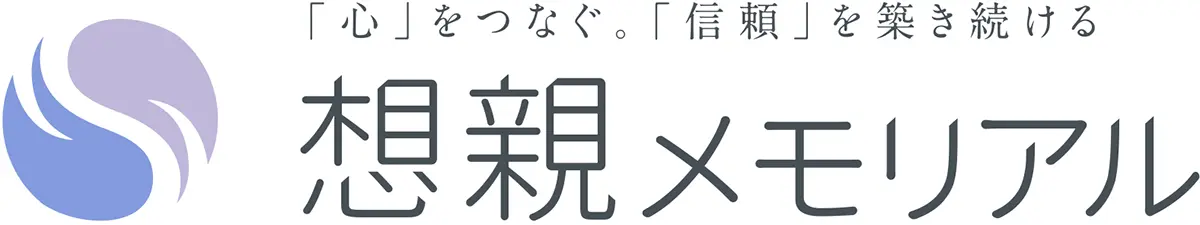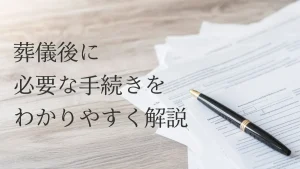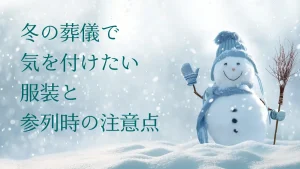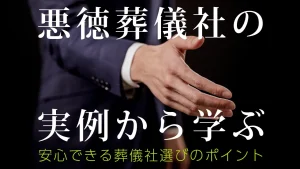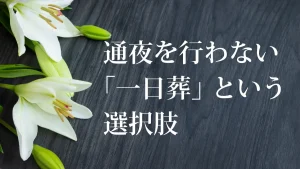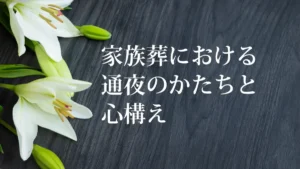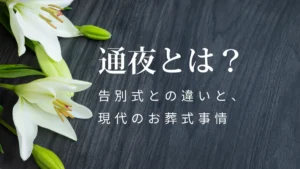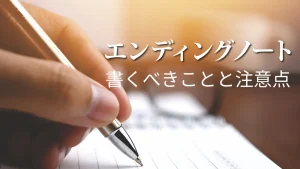1. 家族葬における香典の扱い
家族葬では、参列者を親族やごく近しい方に限るため、香典を辞退するケースも増えています。
「香典はご遠慮申し上げます」と事前に案内することで、遺族・参列者双方の負担を減らせるからです。
一方で、香典を受け取る場合ももちろんあります。その場合は四十九日を目安に返礼するのが一般的です。
2. 香典を渡す方法の多様化
参列者の事情によっては、葬儀に出られなくても香典を届けたいというケースがあります。
- 直接手渡し:従来通り、式場受付で渡す方法
- 郵送(現金書留):遠方で参列できない場合に利用される
- 代理で渡す:親族や同僚に託して届ける方法
3. 即日返しの定着と背景
一般葬では参列者が多いため、香典返しを当日に一律で用意する「即日返し」が広がりました。
参列者にとってはその場で受け取れるわかりやすさがあり、遺族にとっても後日の手間を減らせるというメリットがあります。
ただし、家族葬では参列者数が少なく、香典額も個別性が高いため、従来通り四十九日後に返礼する方法を選ぶご家庭も多いです。
このように、香典返しの形は葬儀の内容によって柔軟に変化しています。
4. 香典辞退という選択肢
近年では「香典を受け取らない」という選択肢も一般化してきました。
理由としては、
- 遺族側の金銭管理や返礼の負担を減らしたい
- 親族間の金銭のやり取りを避けたい
といったものがあります。
香典辞退をする場合は、案内状に「誠に勝手ながら香典は辞退申し上げます」と明記することが大切です。
ただし、実際には、過去にご自身が香典をお渡しした相手が参列される場合など、辞退していても受け取りをお願いされるケースもあります。
「香典は弔意の証」と考える方もおり、特に家族葬の場合は事前の調整が大切です。
5. 今後の香典マナーの変化
- 家族葬の定着:小規模で落ち着いた葬儀が増えることで、香典の扱いもシンプルに
- 香典辞退の拡大:形式よりも負担軽減を重視する流れ
- 渡し方の多様化:郵送・代理といった柔軟な対応が広がる
従来の形式を重んじる方と、現代的な簡素化を望む方が混在するため、「地域や親族の慣習に合わせつつ、無理のない形を選ぶ」ことが、これからの香典マナーといえるでしょう。
6. まとめ(時代に合わせた香典のあり方)
香典の習慣は、今も大切に受け継がれていますが、その形は時代や葬儀の規模に合わせて変化しています。
家族葬が一般化した今、香典を「受け取るか辞退するか」「即日返しにするか忌明け返しにするか」など、選択肢は多様になりました。
大切なのは、遺族・参列者双方にとって負担が少なく、心が伝わる形を選ぶことです。